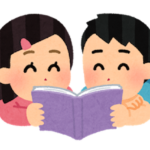建築本の古典を見直してみると、学生時代をは違う発見があるかもしれません。学生の人は、挫折覚悟でぜひとも一読を!末永く楽しめるスルメのような古典の魅力もなかなか良いですよ!


本記事の内容
本記事では、だいたい学校や建築事務所の所長などから読んでよくべき建築書として挙げられる有名な書籍を厳選して載せました。建築入門者も、実務をやっている建築家も、ひさしぶりに建築書を見ていると、新しい発見があるかもしれません。
建築を始めた人も、途中の人も、実務の人も、退職の人も、なんだか時々立ち止まって、読みたくなるのが古典です。古典とはいっても、近代建築までのものと大きく定義しておきましょう。きっと、どのタイトルも最後まで読めたり、読めなかったり、忘れてしまったり、学生の時の良い思い出と、大変な思い出と交錯しているかと思います。または、大学や専門学校の先生に、「この本は、読みなさーい!」とハッパかけられているかもしれません。でも「読め!」と言われて読む本ほど面白くないものはない!!また実務のときは、忙しくて本を読んでいる暇なんてないと思います。
しかし、時々原点に立ち戻る時も必要です。
やっぱり、数十年、あるいは数百年という時を経ても残っている「古典」には、通奏低音として普遍的な哲学が流れています。そして、そんな古典を紐解くと、自分が建築をやりたかったとこのことを思い出すと思います。久しぶりに、如何でしょう?ちらりとめくってみては!
目次
- 建築論 レオン・バティスタ・アルベルティ
- 建築四書 アンドレア・パラディオ
- ピラネージ建築論 対話 ピラネージ
- ウィトルーウィウス建築書 ウィトルーウィウス
- 現代建築史 ケネス・フランプトン
- 明日の田園都市 エベネザー・ハワード
- ポストモダニズムの建築言語 チャールズ・ジェンクス
- 都市のイメージ ケヴィン・リンチ
- コラージュシティ コーリン・ロウ
- ラスベガス ロバート・ヴェンチューリ
- 建築の多様性と対立性 ロバート・ヴェンチューリ
- 第一機会時代の理論とデザイン レイナー・バンハム
- 空間・時間・建築 ジークフリート・ギーディオン
- 現代建築入門 ケネス・フランプトン
- 建築家なしの建築 バーナード・ルドルフスキー
- 錯乱のニューヨーク レム・コールハース
- アメリカ大都市の生と死 ジェイン・ジェイコブズ
- テクトニック・カルチャー ケネス・フランプトン
- パタン・ランゲージ クリストファー・アレグザンダー
- マニエリスムと近代建築 コーリン・ロウ
- 光の合成に関するノート 都市はツリーではない クリストファー・アレグザンダー
- 都市の建築 アルド・ロッシ
- 日本の建築 太田博太郎
- 日本建築史序説 太田博太郎
- 建築史研究の新視点<1>建築と障壁画 西和夫
- 建築史の先達たち 太田博太郎
- 日本の民家 今和次郎
- 隠喩としての建築 柄谷行人
- 建築の解体 磯崎新
- 空間へ 磯崎新
- 装飾と犯罪 アドルフ・ロース
- 住宅論 篠原一男
- 建築をめざして ル・コルビュジエ
- 建築史の基礎概念 パウル・フランクル
- 日本の都市空間 都市デザイン共同体
- 民家は生きてきた 伊藤ていじ
- ゲニウス・ロキ 建築の現象学をめざして ノルベルク=シュルツ
- ルイス・カーン建築論集 ルイス・カーン
- 建築意匠講義 香山壽夫
- 都市の文化 ルイス・マンフォード
- 日本の風景・西洋の景観 オギュスタン・ベルク
- 建築と断絶 バーナード・チュミ
- 都市の原理 ジェーン・ジェイコブズ
- 建築の七燈 ジョン・ラスキン
- モデルノロヂオ 考現学 今和次郎
- アルド・ロッシ自伝 アルド・ロッシ
- 時を超えた建設の道 クリストファー アレグザンダー
- 床の間 太田博太郎
- 吉阪隆正著作集 吉阪隆正
- 輝く都市 ル・コルビジェ
- 黒川紀章著作集 黒川紀章
- 建築の前夜―前川國男文集 前川國男
- 忘れられた日本 ブルーノ・タウト
- 日本美の再発見 ブルーノ・タウト
- 街並みの美学 芦原義信
- 広場の造形 カミロ・ジッテ
- 見えがくれする都市 槙文彦
- 日本デザイン論 伊藤ていじ
- 代謝建築論 菊竹清訓
- 自然な構造体 フライ・オットー
- 都市への権利 アンリ・ルフェーブル
- 西洋建築史図集 日本建築学会
- 陰翳礼讃 谷崎潤一郎
- 新訳 茶の本 岡倉天心
- 環境としての建築: 建築デザインと環境技術 レイナー・バンハム
- かくれた次元 エドワード・T・ホール
- 空間の経験―身体から都市へ イーフー・トゥアン
- 人間の空間―デザインの行動的研究 ロバート・ソマー
- 人間の街: 公共空間のデザイン ヤン・ゲール
- 建物のあいだのアクティビティ ヤン・ゲール
建築入門書【62選】古典、近代、現代建築まで厳選
1. 建築論 レオン・バティスタ・アルベルティ
Leon Battista Alberti(1404-1472)によるラテン語テキスト「De Re Aedificatoria」の英訳版「The Ten Books of Architecture: The 1755 Leoni Edition」のさらに日本語版だと思われます。
建築理論に関する最初期のテキストです。本テキストの建築への重要性は計り知れません。
アルベルティの理論家としての名声が確立された本であり、建築理論の最初に立ち戻る重要書籍です。
2. 建築四書 アンドレア・パラディオ
建築家Andrea Palladioによって1570年に建築四書(libri dell’architettura)が出版されました。本書は、原文がイタリア語で書かれた建築に関する初期の論文です。なぜ四書かというと、ヴェネツィアで4巻として最初に出版されたからです。また、作者自身の絵を元にして、木版画が作られました。
ここでは、建築書の詳細な注釈書について紹介します。
3. ピラネージ建築論 対話 ピラネージ
ピラネージによる建築論 「PARERE SU L’ARCHITETTURA」 の和訳です。内容紹介をみると、「ドリス、イオニア、コリントがほんとうに重要なオーダーであると信じているのですか?」という問いかけをするピラネージの言葉が載っています。古典主義の建築を乗り越えようとした当時の思考が見えてきます。
4. ウィトルーウィウス建築書 ウィトルーウィウス
ウィトルーウィウスはローマの建築家です。紀元前前46~36年頃に活動したといわれています。カエサルのアフリカ戦役にも従軍して、紀元前25年に「De Architectura」(建築書)を著わしました 。全10巻からなり「建築十書」ともよばれています。
本書は古代の建築技法書としては、唯一完全な形で残っているものです。1414年にザンクト・ガレン修道院で写本が見つかったのがきっかけで多くの人に読まれることになりました。ザンクト・ガレン修道院は、現在も多くの古代からの書籍が残っていて有名です。
この書籍が、ルネサンス期の建築家の必読書となったことから、上記にあるアルベルティらの建築論が生まれたといえます。現存する最も古い刊本は、86年頃ローマで刊行されたものです。その意味では原点ですね。建築「De Architectura」という概念を知るにはもってこいでしょう。
5. 現代建築史 ケネス・フランプトン
現代建築史ですが、近代建築に位置付けられるオッアドラー、サリヴァンからヴァン・ド・ヴェルド、ル・コルビュジエ、ミースなどの論説から、現代建築家の安藤忠雄まで論じられています。フロンプトンが編み出した、構築性や批判的地域主義などの言説を用いて、建築におけるモダニズムの思考について論じられています。建築史の基本書です。
6. 明日の田園都市 エベネザー・ハワード
近代都市計画の父であるハワードによる書籍です。住民を中心として考える初めての都市計画論といえます。
都市の環境悪化と荒廃からハワードは新しい田園都市を構想しました。それは当然、当時の社会様式、経済システムや事業収益などに裏打ちされたものでした。彼の都市計画のデザイン部分に関しては、当時の最新のテクノロジーを取り入れたものであったといえます。
今の最近のテクノロジーを入れた都市計画と住宅はどうなのでしょうか?そんなことを想起させます。新しい都市計画アイデアのきっかけにいいですね。
7. ポストモダニズムの建築言語 チャールズ・ジェンクス
チャールズ・ジェンクス は建築理論家であり評論家です。また、ランドスケープデザイナーでもあります。彼のモダニズム、ポストモダン建築に関する鋭い批評には、多くの支持者がいます。また、ジークフリード・ギーディオンとレイナー・バンハムを師事していたことでも知られています。ポストモダン建築までの建築言語を知る上で重要な資料を得ることができます。
目次
第一部 モダニズム建築の死
・建築の危機
・ユニヴァレントな形態
・ユニヴァレントな形式主義者と軽卒な象徴主義者と
第二部 建築におけるコミュニケーション方式
・メタファ
・単語
・シンタクス
・セマンティクス
第三部 ポスト・モダニズムの建築
・歴史主義、ポストモダニズムの起源
・直進的復活主義
・ネオ・ヴァナキュラー
・ラディカルな折衷主義 等
8. 都市のイメージ ケヴィン・リンチ
都市デザインへの革命的な概念であるイメージアビリティを提唱した本です。ケヴィン・リンチの卓抜な視点は、現在も通用する視点と言えます。都市に暮らす人びとの視覚・心理・行動様式に着目しており、行動心理学、文化人類学的な要素も垣間見られる非常に読みものてきにも面白い本です。フィールド調査の参考にもなります。
9. コラージュシティ コーリン・ロウ
コーリン・ロウによる名著です。都市を歴史のコラージュと捉え、都市は記憶の劇場であると同時に、未来を予言する場でもあると考えています。
10. ラスベガス ロバート・ヴェンチューリ
ロバート・ヴェンチューリは「母の家」でも知られる有名な建築家です。本書は一連の近代主義建築批判の流れを踏襲しています。
本書では近代建築に対応する場所として、ラスベガスをとりあげています。ラスベガスの建築群に現れる多様性と対立性を、『ラスベガス』のあひるを取り上げながら解説しています。近代主義が機能性を重視した結果生まれた無装飾な建築が、実際には形態主義、表現主義、象徴主義へ進むという皮肉な結果に進んだという指摘は、今も当てはまります。読み返してみるとわかりやすい論考です。
11. 建築の多様性と対立性 ロバート・ヴェンチューリ
『建築の多様性と対立性』(1966)は、上記の『ラスベガス』に先立って上梓されたロバート・ヴェンチューリによる著作である。ヴェンチューリの「less is bore」という言葉は、ミース・ファン・デル・ローエの「less is more」を皮肉ったレトリックとしても知られています。
本書は、80年代以降に隆盛するポストモダニズム建築の理論的な背景を提供しているという意味で、極めて先見性の高い著作と言えます。
12. 第一機械時代の理論とデザイン レイナー・バンハム
この書籍を勧められた建築関係者は多いのではないでしょうか?かなり厚い本ですべてを読むのはなかなか苦労します。本書は、近代建築の成立からその発展までを、多くの建築家らの理論的著作、建築物、プロジェクト、絵画・彫刻などから分析しています。今も多くの論考に引用されるの最重要な建築書のひとつです。
13. 空間・時間・建築 ジークフリート・ギーディオン
ジークフリート・ギーディオンは、スイスの建築史家、都市史家、建築評論家です。『空間・時間・建築』はその中でも最も知られた著作の一つです。建築をやっていて、知らない人はいないと思います。CIAMの発起人の一人であり、近代建築の理論家の最重要人物です。
冒頭に『われわれの文化の現状に対して危惧を感じ、その対立的な諸傾向の外面的な混乱から脱出する道を見出そうと苦慮している人たのために書かれたものである』とあります。今の時代に建築が何ができるか考えるのに必須の書です。
14. 現代建築入門 ケネス・フランプトン
英語版の『The Evolution of 20th Century Architecture: A Synoptic Account』の翻訳です。ル・コルビュジエ、フランク・ロイド・ライト、アルヴァ・アールト、ルイス・カーン、レンゾ・ピアノ、安藤忠雄など代表的な建築家に焦点を当てています。
彼のアプローチは非常に明確です。彼は、建築の革新を推進する力として4本の線をあげています。そしてその線が重複していることが重要です。時系列に1本の線ではなく、複数の線が重複するのです。1番目の線はアバンギャルド(1887-1986)。 2番目の線は有機アーキテクチャ(1910-1998)、3番目の線はモダンスタイルとナショナルスタイル(1935-1998)、4番目の線は工業化とプレファビリケーション(1927-1990)です。彼は、建築の背後にある歴史、理論、作られる動機といった観点を縦横無尽に行き交いながら理論展開します。今日の建築の歴史を「アヴァンギャルド/伝統」「有機主義」「普遍文明/国民文化」「生産/場所」などのテーマから読み解いています。
15. 建築家なしの建築 バーナード・ルドルフスキー
英語版『Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture』の翻訳である。
これについては説明はほとんどいらないでしょう。地下の家、遊牧民と水生の家、丘の町、要塞化された村、アーケード、屋根付きの通り、修道院、穀物倉庫、円形劇場など、まずは本を開いてみましょう!
16. 錯乱のニューヨーク レム・コールハース
レム・コールハースによると、「ニューヨーク」は都市と人間の間の信じられないほどの多様性に満ちたメタファーで占められているとしています。 19世紀の終わりから始まった人口、情報、および技術の急速な進展により、マンハッタンは、大都市のライフスタイルと建築のための膨大な実験場となったのです。
「マンハッタン」は、ユートピアの破片(ロックフェラーセンター、国連ビル)や、不合理な現象(ラジオシティミュージックホール)などによって占められています。コールハースは、マンハッタングリッドの設置、コニーアイランドの創設、超高層ビルの開発など、ニューヨークの歴史を物語る数々のエピソードで、建築と文化の動的な関係を再解釈しています。
再度読んでみると、新しい発見があるはずです。
17. アメリカ大都市の生と死 ジェイン・ジェイコブズ
作家兼活動家のジェイン・ジェイコブズによる1961年の書籍です。内容としては、主に1950年代の都市計画政策についての批判です。近代都市計画を批判して、都市の有機的で多様性に魅力を見出す視点を提示しています。
ロバート・ベンチューリの『建築の多様性と対立性』(1966)と同時期なので、時代の産物とも言えます。上記と一緒に比較しながら読むと面白いです。
18. テクトニック・カルチャー ケネス・フランプトン
テクトニックカルチャーには、10のエッセイがあります。それぞれのエッセイは、18世紀から現在までに書かれたフランス語、ドイツ語、および英語のテキストに対するフランプトンによる綿密な解釈に基づいています。建築を結構術(テクトニックス)をキーワードに読み解く視点は、フランプトンならではです。分厚い書籍なので、読み直しがいがあります。
19. パタン・ランゲージ クリストファー・アレグザンダー
多くの人が持っている本ではないかと思います。説明はいらないです
都市計画と建築に関して、さまざまな有機的な建築・都市環境作りのプロセスを示しています。253のパターンと800の挿図があります。
20. マニエリスムと近代建築 コーリン・ロウ
英語版『The mathematics of the ideal villa and other essays』の翻訳です。
ル・コルビュジェのガルシュの住宅(1927)パラディオのヴィラ・マルコンテンタ(1560)との類似性を初めて指摘した論考が有名です。久しぶりに読んでみると、初学者の頃を思い出します。
- 目次
- 序
- 理想的ヴィラの数学
- マニエリスムと近代建築
- 固有性と構成 あるいは十九世紀における建築言語の変遷
- シカゴフレーム
- 新「古典」主義と近代建築 I
- 新「古典」主義と近代建築 II
- 透明性 虚と実
- ラ・トゥーレット
- ユートピアの建築
21. 光の合成に関するノート 都市はツリーではない クリストファー・アレグザンダー
クリストファー・アレグザンダーといえば、「都市はツリーではない」の言葉で知られています。数学的手法としてのツリー構造とセミラチス構造を建築、都市の秩序へ応用し、建築、都市や美しさを自覚的に生み出すプロセスを追究する原点となった著作です。その後、「パタン・ランゲージ」へ繋がっていきます。
そんなに長くないので、ぜひ読み直してみてくださいね!基本書籍としておすすめです。
22. 都市の建築 アルド・ロッシ
アルド・ロッシは、イタリアの建築家です。特に1980年代を中心に、建築理論、ドローイング、設計の分野で活躍しました。また、現代建築界の重要な論客でもあり、本書はロッシの主著です。
今はもう古典といってもよいレベルなっているので、読んでいない人はぜひとも手に取ってみましょう。
23. 日本の建築 太田博太郎
まだ建築を始める前に読んだ本です。かなり容易に読めるのですが、内容は深く、面白いです。
日本固有の建築がどのように構築され、発展してきたのかについて、伊勢神宮・法隆寺・桂離宮・金閣寺・銀閣寺を例にしながら記述しています。中国からの外来様式の影響を受けつつも、日本独自のかたちの変化してきたプロセスが浮かびあがります。仏教建築!面白い!と思いを新たにすること間違いなしです。日本文化論としてもどうぞ。写真・図版多数。
24. 日本建築史序説 太田博太郎
日本建築史の概説書であり、構造とデザインの通史。60年以上読み継がれるベストセラーです。まずはこれから。
- 目次
- Ⅰ 日本建築の特質
- Ⅱ 日本建築史序説
- Ⅲ 日本建築史の文献
- Ⅳ 続 日本建築史の文献
25. 建築史研究の新視点<1>建築と障壁画 西和夫
本書は建築史家である西和夫の論文の中から障壁画と建築についてまとめたものです。歴史研究にどのような視点が導入できるのか知る上でも、参考になります。
- 目次
- 第1編 建築と障壁画の復原検討二条城二の丸諸御殿、大仙院、南禅寺、日光院、円満院、大覚寺寝殿
- 第2編 建築と障壁画の諸問題勧学院、光浄院、名古屋城本丸御殿、霊雲院、勧修寺、奥能登時国健太郎家住宅、瑞峯院、阿弥陀寺、正法寺、知恩院、聖衆来迎寺、光明寺、泉涌寺
- 第3編 障壁画制作とその背景内裏、江戸城
26. 建築史の先達たち 太田博太郎
建築史学を目指す人が最初に読むべき本かもしれません。読み物としても、かなり面白いです。
建築史学の先人たち、伊東忠太、関野貞、天沼俊一、長谷川輝雄、足立康、堀口捨己、浅野清などのエピソードが出てきます。また太田博太郎がどのように彼らの影響を受けながら研究を進めてきたのかについても知ることができます。極めて興味深いのに、読みやすい入門書です。
残念ながら絶版です。古書などが見つかれば即買いと私は思います。
Amazonにもないので、もし見つかればアップします。
- 目次
- Ⅰ. 建築史の先達たち
- Ⅱ. 建築史への道
27. 日本の民家 今和次郎
今和次郎は、民俗学者の柳田国男と一緒に民家調査を行なっています。なかなか面白いコラボレーションです。農村の建築に価値を見出す視点は、考現学にもそして不完全なものに価値を見出すような民芸などにも通じます。
- 目次
- 日本の民家(田舎の人たちの家;構造について;間取について)
- 間取の由来考
- 採集
- 調査(相模国津久井郡内郷村;武蔵国秩父郡浦山村;武蔵国南多摩郡恩方村)
28. 隠喩としての建築 柄谷行人
思想の起点として建築を考えてみるときの必須の書です。英語版はMITから出ていてこちらも有名です。
「私が本書でやろうとしたことは,ディコンストラクションをコンストラクションから,すなわちケンチクから考えてみることだといえる」(英語版への序文)
29. 建築の解体 磯崎新
これは、特に説明がいらないと思います。必須の書です。1975年美術出版社刊の復刻版です。ホライン、アーキグラム、ムーア、アレグザンダーなど合計7人の建築家について論じています。
- 目次
- ハンス・ホライン―観念の触手で環境を捕獲する
- アーキグラム―建築を情報に還元する
- チャールス・ムーア―伝達メディアとしてのポップ建築
- セドリック・プライス―システムのなかに建築を消去する
- クリストファー・アレグザンダー―環境を生成する普遍言語を探る
- ロバート・ヴェンチューリ―現代マニエリスムとしての混成品建築
- スーパースタジオ アーキズーム―概念建築による異議申し立て
- 『建築の解体』症候群
30. 空間へ 磯崎新
磯崎新のエッセイ集です。様々な出版媒体に1960年代に出された論文・エッセイです。
- 目次
- 1960(現代都市における建築の概念;シンボルの再生;孵化過程 ほか)
- 1962(プロセス・プランニング論;都市デザインの方法;日本の都市空間 ほか)
- 1964(虚像と記号のまち ニューヨーク;世界のまち;死者のための都市―エジプト ほか)
- 1966(媒体の発見―続プロセス・プランニング論;幻覚の形而上学;マリリン・モンロー様 ほか)
- 1968(凍結した時間のさなかに裸形の観念とむかい合いながら一瞬の選択に全存在を賭けることによって組立てられた“晟一好み”の成立と現代建築のなかでのマニエリスト的発想の意味;梱包された環境;占拠されたトリエンナーレ ほか)
31. 装飾と犯罪 アドルフ・ロース
装飾は犯罪である。という文句は建築をやっている人では聞いたことのない人はいないとおもいます。しかし、実際の本を読んで原典をみた人は少ないのでは?
以下の目次を見るだけでも雰囲気がわかりますが、ぜひともこの機会に、原典を確認してみてください。
- 目次
- ウィーン・プラターの旧万国博覧会、ロトンダ展示会場において展示された室内空間について
- デラックスな馬車について
- 建築材料について
- 被覆の原則について
- ポチョムキンの都市
- 女性と家
- 建築における新・旧の二つの方向―最近のウィーンの芸術思潮を十分考慮した上での比較検討
- 馬具職人
- ウィーンにおける最も素晴らしい内部空間、最も美しい貴族の邸館、最も美しいが近々取り壊しの運命にある建築物、最も美しい新建築、最も美しい散歩道
- 住居の見学会
- 余計なこと(ドイツ工作連盟)
- 文化の堕落について
- 装飾と犯罪
- ミヒャエル広場に面して立つ建物についての二つの覚え書きとその補章
- 建築について
- 私の建築学校
- ベートーヴェンの病める耳
- カール・クラウス
- 郷土芸術について
- ペーター・アルテンベルクとの別れにあたって
- 住まうことを学ぼう!
- シカゴ・トリビューン新聞社社屋-柱としての建築
- アーノルド・シェーンベルグと同時代人達
- 近代の集合住宅
- ヨーゼフ・ファイリッヒ
- オスカー・ココシュカ
32. 住宅論 篠原一男
篠原一男が30代から考えた住宅に関する12編のエッセイが収録されています。
清家清に師事して、プロフェッサーアーキテクトとして住宅を中心に設計をしてきた篠原一男の、最初の決意表明と言えます。
活字にすること、大事だなと思わされます。
- 目次
- 日本伝統論
- 無駄な空間
- 住宅は芸術である
- 様式がつくられるとき
- 失われたのは空間の響きだ
- 装飾空間のための覚え書き
- 三つの原空間
- 住宅設計の主体性
- 原型住宅の提案
- 黒の空間
- 空間の思想化
- 空間の思想と表現
33. 建築をめざして ル・コルビュジエ
あまりにも有名な言葉「住宅は住むための機械だ」、「建築を目指して」はル・コルビュジエの建築に対するマニフェストです。
みなさんも、自分のマニフェストはありますか?書くこと、上記の篠原一男の住宅論もそうですが、「何か活字にしておくこと、表明すること」は、大きなことをやり遂げるためには大事ですね。
34. 建築史の基礎概念 パウル・フランクル
本書は建築史・意匠論の概念確立をめざしています。建築を軸とした空間論の古典といえます。一方で、こうした壮大な目標は時に本の目的も見失ってしまいます。しかし、個別の話に終始するのではなく、大きな建築という大きな抽象論へ集約させるための取り組みには大いに学ぶところがあります。
細分化された学問領域をもう一度、大きな視点から繋いでいく考え方も必要です。
35. 日本の都市空間 都市デザイン共同体
西欧を中心に発展したきた都市空間の研究に対して、日本の伝統的な都市空間に着目し、その形式を再評価した必読書。ロングセラーです。
- 目次
- Ⅰ都市デザインの方法
- Ⅱ形成の原理
- Ⅲ構成の技法
- Ⅳ要素の作用
- Ⅴ実例の検討
- Ⅵ表現の技法
36. 民家は生きてきた 伊藤ていじ
民家研究の名著の復刻版です。
伊藤ていじは、1922年生まれの日本を代表する建築史家のひとりで、関野克のお弟子さんにあたります。磯崎新や川上秀光と八田利也(はったりや)のペンネームで、多くの建築評論をしていたこともで知られています。
他にも『日本の民家』(二川幸夫撮影、美術出版社)は有名な本で、1963年に初版が出版され、毎日出版文化賞を受賞しています。
37. ゲニウス・ロキ 建築の現象学をめざして ノルベルク=シュルツ
ゲニウス・ロキ(genius loci)とは、ローマ神話にでてくる土地の守護精霊のことです。日本語では地霊とも翻訳されています。通常の用法では、土地の本来持っている歴史や地理的な要因から現れる雰囲気や、いわゆる土地柄的なものを意味しています。
ここでは、プラハ、ハルトゥーム(ナイル河沿岸の植民都市)、ローマの3都市を例について、場所の視点で読み解いています。
翻訳もうまいし、なにより注釈を含めた編集構成がよいと松岡正剛さんもおすすめしています。
あとは、鈴木博之による「東京の地霊(ゲニウス・ロキ)」も有名な書籍です。読んだ人も多いかと思います。
38. ルイス・カーン建築論集 ルイス・カーン
ルイスカーンの建築論をわかりやすく概説した書籍。ルイスカーンが使う建築用語がわかりにくいなと思っている人には、特におすすめです。
なんとなく分かっていたような概念や単語が、「腹落ち」する感じです。
39. 建築意匠講義 香山壽夫
東京大学教授で建築家であった香山壽夫の書籍です。建築に興味のある人におすすめする平易ですが、内容は充実している専門書です。
人が建築する時の楽しさ、喜び、作る好奇心をを掻き立てます。平易な言葉によって書かれているのでわかりやすいです。
40. 都市の文化 ルイス・マンフォード
建築を単体ではなく、都市全体の中で捉えた時都市研究が必要となります。その都市研究の書籍の金字塔といえます。中世時代から現代の巨大都市まで網羅した都市研究の最重要書籍の一つです。
「都市の文化」のオリジナルは1938年に出版されました。他にも興味があれば、英語版ですが、以下の書籍をどうぞ。
- The Culture of Cities (1938)
- City Development (1946)
- City in History (1961)
- The Urban Prospect (1968)
41. 日本の風景・西洋の景観 オギュスタン・ベルク
モダンとポストモダンの関係を、ヨーロッパの近代景観論(主客分離)と日本の事例に中で紹介しています。
ポストモダンにより主体客体二元論である近代景観論が解体され、「造景」の時代がうまれる。つまり景色を見るということは参加するということ。
これは、近代の観光学とも似ています。都市景観、都市開発、観光学に興味のある人にもおすすめです。
42. 建築と断絶 バーナード・チュミ
ポストモダン思想と建築の関係を知る上で重要な書籍です。
モダニズムは、「形」と「機能」の連続性を主張しました。ポストモダニズムは、「形」と「意味」の連続性を主張しました。チュミは、そのような形との連続した関係性を真っ向から否定しています。
つまり形から機能は生み出されないし、形から意味も生み出されない。それぞれの要素は断絶をしているということです。
ではどうやって建築を作るのでしょう?人と建築の間にある関係性を、無関係から一体化した関係の間にある無数の状態のバリエーションから、選ぶ、並べる、そのまま置くといった行為によってしか作り得ないとします。
もう一度読み直してみたい書籍です。
43. 都市の原理 ジェーン・ジェイコブズ
ジェイコブズによる都市経済論です。ジェイコブズは、都市研究家であり作家です。1952年から「アーキテクチュラル・フォーラム」誌の編集メンバーとして活動し、最も有名な著書として『アメリカ大都市の死と生』があります。
本書は都市の成長や衰退や、都市と農業の関係などを経済学的側面から分析している理論書です。
44. 建築の七燈 ジョン・ラスキン
ジョン・ラスキンは、19世紀のイギリスを代表する美術評論家です。芸術家のパトロンとしての側面もありましたが、自分で設計製図や水彩画をこなす芸術家としての側面も持っています。ラスキンの『近代画家論』の有名です。
「建築の七燈」は、当時の建築における美的意匠の形成と、建築家の役割について7項目に分けて解説しています。
近代化のなかで多くの破壊の恐れのあったゴシック建築について、その本質を説いています。
これこそ。ザ古典です!ご賞味ください!
45. モデルノロヂオ 考現学 今和次郎
残念ながら、現在は絶版ですが中古本があります。
今和次郎は、柳田國男の教え子であり民俗学研究者です。建築学の観点から住居や服飾に関しても研究してきた研究者です。
「考現学」を提唱して、建築学、住居生活や意匠研究などでも活躍しました。早稲田大学理工学部建築学科の教授であり、日本建築士会会長なども務めた教育者です。
これは、好きな人はもうきっと読んでいると思います。必読書です!
復刻版でもかなり高額古書なのでいいのがあったときに・・・。
46. アルド・ロッシ自伝 アルド・ロッシ
アルド・ロッシによる自伝。ロッシの様々なプロジェクトや建築の理論的な過程がまとまっています。基本書としておすすめです。
- 目次
- 学としての自伝
- ドローイング 1980年夏
- 後記形態におけるイデオロギー
47. 時を超えた建設の道 クリストファー アレグザンダー
パタン・ランゲージ以後の重要書籍の一つです。
建築を実際に作る際に行うさまざまな計画に対して新しい取り組み方法を提案しています。
建築事務所にない人は、新人さん向けに買って良いと思います。必読書のひとつです。
48. 床の間 太田博太郎
床の間ってなに?
建築学科では、床の間については教えてくれません。大学で建築を学ぶと、基本的には近代建築の流れがほとんどであると思います。
もし大学で床の間について詳しく学んだとすれば、私はその学校が大好きになりそうです。
床の間は、いつ、どのように作られ、どのように変わったきたのでしょうか。読んでみて「そうだったのかぁー」と思うこと間違いないです。
49. 吉阪隆正集 吉阪隆正
絶版書です。言わずもがな、必須本です。見つけたらなくなる前に買いましょう。
体系的な本というよりも雑多な内容を含みますので、時代によって思索が変化していっていることもよくわかります。読み物としても面白いので、私のおすすめです。
50. 輝く都市 ル・コルビジェ
「輝く都市」はル・コルビュジエのもっとも有名な都市計画案であり、かつ書籍と言えます。これ以後の、建築と都市計画に大きな影響を与えてきました。「輝く都市」を実現するための当時の設計理念はどのようなものだったのでしょうか?必読書です。
他のも興味があればこちらの書籍は日本語で読めます。
- 『建築をめざして』
- 『今日の装飾芸術』
- 『ユルバニスム』
- 『伽藍が白かった時』
- 『近代絵画』
51. 黒川紀章著作集 黒川紀章
本書は、黒川紀章の全集である。黒川紀章の主要著作を「評論・思想」「建築論」「都市論」「対談」「論文・講演・インタビュー」「研究」「展覧会カタログ」「翻訳」「主要作品図録」に分けてまとめてある。
全巻はちょっと読み通せないボリュームなので、必要な書籍を購入するのが良いと思います。以下の目次を見るだけでもかなり面白そうです!
- 目次
- 1巻評論・思想Ⅰホモ・モーベンス、ノマドの時代、情報列島日本の将来
- 2巻評論・思想Ⅱグレーの文化、時評日本の断面
- 3巻評論・思想Ⅲ黒川紀章ノート
- 4巻評論・思想Ⅳ新・共生の思想
- 5巻建築論Ⅰ行動建築論、プレファブ住宅、空間の思想
- 6巻建築論Ⅱ現代建築の創造、建築論Ⅰ
- 7巻建築論Ⅲ建築論Ⅱ、花数寄、クアラルンプール新国際空港
- 8巻建築論ⅣMetabolism in Architecture、Rediscovering Japanese Space、New Wave Japanese Architecture、Das Kurokawa Manifest
- 9巻都市論Ⅰ都市デザイン、道の建築、都市学入門
- 10巻都市論Ⅱ都市の思想、メタボリズムの発想
- 11巻都市論Ⅲ東京改造計画の緊急提言、TOKYO大改造、都市革命
- 12巻対談どうする21世紀 パートⅠ〜Ⅲ
- 13巻論文・講演・インタビュー−
- 14巻研究都市間交通におけるV/STOL機の役割
- 15巻展覧会カタログ黒川紀章回顧展 共生の思想、アパートメント・アヴァンギャルド、IL FUTURO NELLA TRADIZIONE、Le-Metabolisme 1960-1975、Retrospective Penser la Symbiose、London Texts、Metabolism and Symbiosis
- 16巻翻訳アメリカ大都市の死と生、現代建築講義 (抄)
- 17巻主要作品図録Ⅰ−
- 18巻主要作品図録Ⅱ−
52. 建築の前夜―前川國男文集 前川國男
前川國男自身の文章を通して、ル・コルビジェに学んだ建築家前川國男が追い求めた近代建築について知ることができます。
装幀は亀倉雄策が担当しています。
- 目次
- 文集によせて 大谷幸夫
- Mr.建築家-前川國男というラディカリズム 布野修司
- I 1930-1945年
- II 1945-1959年
- III 1960-1969年
- IV 1970-1986年
- 対談 建築家の思想 前川國男・藤井正一郎
- 年表
- 文章目録・補遺
- 執筆者略歴
- 出版まで あとがきに代えて 藤原千晴
53. 忘れられた日本 ブルーノ・タウト
ブルーノタウトは、ドイツので1933年から3年間、日本に滞在しています。その時に多くの日本の建物をみて、当時の近代化に向かう日本の世情の中で、日本の良さを再発見します。
こうした他者による自国の再発見の構図は、他の国もで結構みられます。タウトは、桂離宮、伊勢神宮、床の間、日本の農家、心、禅、など日本人の心と文化を読み解きます。必読書です。
54. 日本美の再発見 ブルーノ・タウト
タウトがいなかったら、日本の伝統的建築の評価観は大きく出遅れていたかもしれません。桂離宮、伊勢神宮、飛騨白川の農家、秋田の民家を通して、日本の美を「再発見」しています。新書なので薄くて、しかし内容は濃くで電車の中や、旅行におすすめです。
55. 街並みの美学 芦原義信
芦原 義信はソニービルや東京芸術劇場などが有名です。また、本書の『街並みの美学』で都市景観の重要性を指摘した先駆者です。
街並みについての書籍は多いですが、日本で「街並み」という言葉を建築界に普及させ、人々が歴史のなかでつくりあげた街並みを建築との関係の中で理論化させました。街づくりのための基本文献です。
56. 広場の造形 カミロ・ジッテ
カミロ・ジッテは、オーストリアの建築家であり、都市プランナーです。近代に基づく効率性を重視した都市計画に異議を唱えて、経済開発優先ではなく文化や芸術の場としての都市空間を提案しました。1843年生まれ、1903年に他界しています。この時にすでに、文化を重視した都市計画を提案しているなんですごいです。こうしてみると、100年前の思索と施策から、なかなか人間は声量しないものですね。
内容は平明な文で書かれています。特に中世ヨーロッパの広場を理解する上での基本図書といえます。
57. 見えがくれする都市 槙文彦
日本を代表する建築家、槙文彦による都市デザイン論です。江戸の町を対象として、複雑な地形をもつ中で町がどのように都市としての形を作ってきたのか、またその形が現代の東京の中では、いったいどのように存在しているのかについて、わかりやすい事例を入れながら解説しています。必読書です。
58. 日本デザイン論 伊藤ていじ
日本デザインの特徴としての「日本的なるもの」を日本の建築・庭園・書道・華道などの特徴から解明しようと試みています。建築・庭園・書道・華道をバラバラのものではなく、その中の特徴の同一性を見ようとする視点は、マクロ視点のデザインの素養を身につけることにつながります。
59. 代謝建築論 菊竹清訓
建築を設計するとはどういうことかを、「か」「かた」「かたち」のキーワードで読み解いています。1969年出版の『代謝建築論』の復刻版です。
- 目次
- はじめに
- Ⅰ デザインの方法論
- Ⅱ 伝統について
- Ⅲ 目に見えるものの秩序
- Ⅳ 目に見えないものの秩序
- Ⅴ 建築は代謝する環境の装置である
- Ⅵ 建築家と思想
- おわりに
- 復刻版おわりに
60. 自然な構造体 フライ・オットー
フライ・オットー はドイツの建築家であり、構造設計者です。特に、博覧会のパヴィリオン建築や競技場建築などに利用するケーブルネット構造、膜構造を使用した大空間が有名です。
本書は、彼の構造設計者としての思想をわかり易く解説しています。また多数の図版と写真があるので、極めてわかりやすいです。技術と建築を自然の関係から理解するための基本書です。
61. 都市への権利 アンリ・ルフェーブル
都市の作られ方をみてみよう!それは、経済優先、投資家優先の都市ではないだろうか?都市とはそこに住む、われわれ“利用者”のためにあるはずなのに。
ルフェーヴルは、消費社会に従属させられてきた現代人の生活を批判し、今こそ人間の主体性を取り戻す時だと主張します。その方法は、遊びやアートへの参加を通して、あたらしい作品となるような都市を創作することであるとしました。
今で言えばコミュニティとの関わりを通して、あるいは参加型という形を通して、都市の再改革を理論面から支える書籍と言えます。
62. 西洋建築史図集 日本建築学会
たまに見直すと全体像が把握できる良い書籍です。建築事務所には必ずあると思いますが、まだ所有していない場合は新人さん向けにあっても良いと思います。
神話の時代から、産業革命直前までの西洋建築がよくわかります。建築士試験対策にもなりますが、少し詳しすぎるかなという感じです。
63. 陰翳礼讃 谷崎潤一郎
陰翳礼讃は、海外で再評価され、芸術や建築の舞台に舞い戻ってきた印象があります。
西洋との本質的な美意識の相違と、かげや隈の内に日本的な美の本質を見る視点、いつ読んでも、読むたびに味わい深い文章です。
64. 新訳 茶の本 岡倉天心
外国にいた岡倉天心が、日本への思いを茶事の物語として書いたエッセイ集です。
建築と茶道の関係はとても重要です。とくに、芸術の鑑賞の仕方についてのくだりは、芸術としての建築面からみてもかなり、面白いと思います。
日本の精神面を見事に捉え得た名著とされています。
65. 環境としての建築: 建築デザインと環境技術 レイナー・バンハム
レイナー・バンハムによる環境デザイン、今で言うサステナブルデザインからみる近代建築史です。
空調、換気、照明、採光などの関係と、フランク・ロイド・ライト、ル・コルビュジエ、ルイス・カーンら建築を引き合いに出しながら論じてます。
まさに、必見ですね。
今の時代にぴったりでもあり、つまり先見の明に満ちた巨匠たち空間設計がよくわかります。
66. かくれた次元 エドワード・T・ホール
この本は、私のバイブル的な本です。
コミュニケーション・建築・都市計画といった分野に対して、空間と文化の視点から、そのかくれた構造を捉えていくものです。
とくに文化へのアプローチがなかなか興味深いですね。
私的・公的な空間への知覚に関して、体験の構造がそれぞれの文化に依拠しながら、微妙に異なる意味をもつことを示しています。
67. 空間の経験―身体から都市へ イーフー・トゥアン
これは、建築の基本用語である「空間」を考えるときの必読書ですね。
人間にとって空間とは何でしょう?
それはいったいどんな経験なのでしょうか。
私たちは、場所にどのような特別の意味を与えているのでしょうか。
こうした疑問に取り組んだ本書は、空間考えるための必須の書籍です。
68. 人間の空間―デザインの行動的研究 ロバート・ソマー
空間についても、いろんな人の意見を読むと面白いですね。
空間とは何かについて、ロバート・ソマーは特に公共的施設における行動面から、建築関係の心理学的な側面に着目しています。
アプローチ方法がとてもユニークです。
69. 人間の街: 公共空間のデザイン ヤン・ゲール
ヤン・ゲールは、都市計画系の勉強をした人の方が馴染みがあるかもしれません。
この本では、街を人間的スケールの集合体として捉え、「生き生きした、安全で、持続可能で、健康的な街」を取り戻す方法について書いています。
実践的な事例が多いので、納得しながら読み進められます。
70. 建物のあいだのアクティビティ ヤン・ゲール
この本は、ヤン・ゲールの古典的名著となっていると思います。
人に焦点を当てて「街に生き生きとしたふれあいを育てる屋外空間」のあり方について語っています。
ヤン・ゲールの都市計画の視点を知ることができるので、まさに入門書としても重要な一冊です。
最後に
みなさん、如何でしたが?ざっと、これだけの書籍を見ていると、懐かしさ半分、そして、元気をもらいませんか?日本語訳されている本がとても多いですね!やっぱり日本はすごいです。おかげで英語の力がなくなってしまいますが。原著もいいものですから、是非興味のあるものは原著も見てみましょう。鹿島出版と彰国社の翻訳文献は群を抜いて多いです。鹿島出版と彰国社に感謝です。建築に疲れてしまった人も、まだまだやる気全開の人も、建築デザインが社会に対してやれることはたくさんある気がします。そして古典を見ると、建築って社会に存在するものだなって思わされます。私も、みなさんと一緒に久しぶりの1冊を手に取ってみます。
ちょっと開いた時間に書籍を聞くサービス
建築をやっているとたくさん本が読みたくなりますが、なかなか時間がない人も多いのでは!
そんな時は「書籍を聞く」こともできます。
特に電車の中などで通勤・通学中の時間に良いと思います。
現在2ヶ月無料体験実施中なので、まずは1度試してみてください。
Amazonプライム Student/学生は6ヶ月無料
AmazonプライムStudentは、学生用のAmazonプライムです。
なんと、書籍のポイント還元最大10%となります。
現在、学生だと6ヶ月は無料で利用できます。
あとは、Amazonプライム映画やドラマなども、見放題なのでとても便利で使えると思います。
Amazonプライム/一般会員は1ヶ月無料
一般会員は1ヶ月無料で利用することができます。
Kindleの利用もできるので、電子書籍はめちゃ便利です。
さらに、Amazonファミリーがあります!
幼い子供がいる方やこれから家庭を始める方のための、Amazonプライム会員限定のサービスです。
上記の、プライム会員(年会費3,900円、税込)に申し込み、お子様の出産予定日/誕生日を登録すると、AmazonプライムとAmazonファミリーの両方の特典を受けることができます。
*Amazonプライムの年間会員費以外の追加料金はありません。